
問題は「納豆」だった。時はバブル。大学生活を謳歌していた頃、週末は栃木県のゴルフ場でキャディのアルバイトをしていた。セルフプレーなど影もなく、バイト集めのために三食賄い付きの寮を備えるゴルフ場も少なくなかった。毎食欠かさずお膳の真ん中で主食を主張する納豆を生粋の関西人である僕にはどうにも受け入れられなかった。
ところが、六十歳を目前にして納豆が食べられるようになる。コロナ禍のビジネスホテルで、朝食のビュッフェが据え膳に変わり、その中央に小さなワラ包みの納豆があった。キャディ寮での景色が脳裏によみがえった。「食べてみるか…」と思った。以来、我が家の冷蔵庫に納豆が常備されている。
「苦手」には遺伝子も深く関わる。「パクチー大丈夫?」とは、タイを訪れる際の挨拶のようなもの。アルデヒド臭を敏感に感知する人は、パクチーの刺激臭を肉の腐敗臭として感じるらしい。僕はパクチーは好きだが、酒だけはどうにもならない。アルデヒド脱水素酵素を持たぬ僕の体は、アルコールの分解で生じるアセトアルデヒドを処理できず、頭痛や吐き気に襲われる。
納豆嫌いは文化の壁にすぎない。だが、パクチー嫌いは遺伝子と記憶が重なる感覚の壁であり、アルコールは遺伝子そのものが立ちはだかる身体の壁となる。
地域独自の発酵食品は、侵略者にとって「腐敗物」であり、収奪されずに残される。保存性と栄養価が高いほどに重宝された。ブルーチーズやキムチもその例だ。文化に刷り込まれた腐敗臭の中に旨味を見つければ、その臭味丸ごと美味となる。
苦手の正体を辿れば、そこには文化と遺伝と歴史がある。源平の争乱に始まる八百年超の東西分断の壁を乗り越えた我が身を寒からしめるのは、積み重ねたOBの系譜である。六番ホールの右OBは今日も怖い。その怖さを美味に変えられぬところに、僕自身の壁がある。遺伝子のせいではない。
内本浩史(うちもとひろし)
BUZZ GOLF 主筆

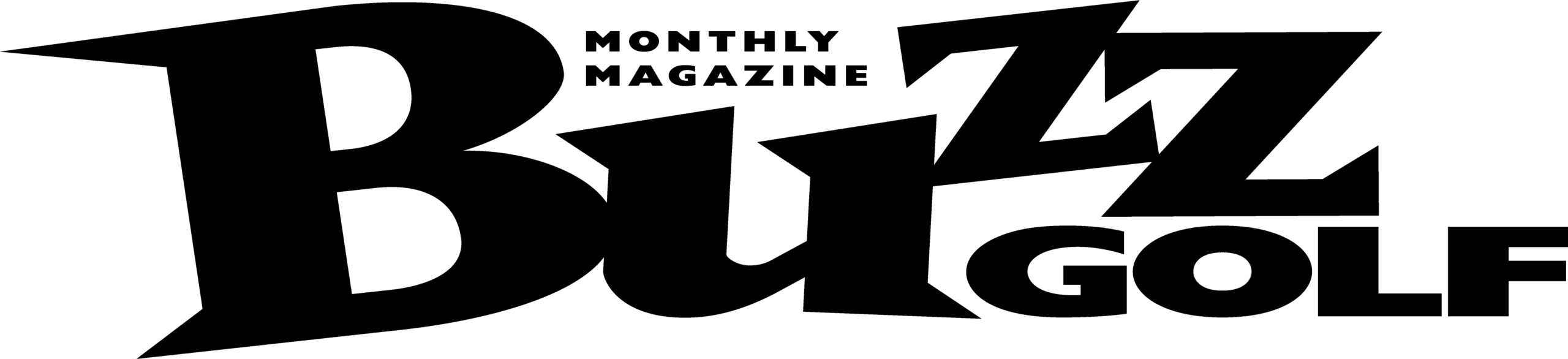


この記事へのコメントはありません。